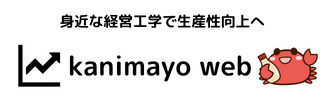このページでは本サイトのベースとなる経営工学について解説。
経営工学とは
経営工学(英名:Industrial Engineering)に関して、日本の関連団体である日本経営工学会・日本IE協会は下記のように表している。
- 経営上の諸問題を発見して解決するための工学的アプローチを基本としたマネジメント技術 (出典:公益社団法人日本経営工学会)
- 価値とムダを顕在化させ、資源を最小化することでその価値を最大限に引き出そうとする見方・考え方であり、それを実現する技術 (出典:日本IE協会)
経営上の諸問題・工学的アプローチ・価値・技術がポイントであり、経営をよりよくするための技術体系とも言える。
2013年に関連する資格のひとつである技術士を取得したが、当時の学習ノートには「経営資源を効率的に運用し、利益の最大化を目指す学問」と自分なりに記していた。
経営工学の特徴
カバーする範囲がとてつもなく広いのが一番の特徴だと思う。
技術士試験の受験時に使用していたテキストである経営工学概論(泉英明=編著)の目次はこちら。
- 企業と社会
- 企業の経営と国際化
- 企業経営と経営工学
- 生産管理
- 品質管理
- 工程管理
- 原価管理
- 作業管理
- 資材管理
- 設備管理
- 人事労務管理
- マーケティング
- 財務管理
- 情報科学
- 数理統計学
- OR(オペレーションズ・リサーチ)
- 人間工学
- 標準化
あまりにも広すぎて自分が専門としている経営工学って何だろうと感じるときもあるが、経営問題の解決≒生産性向上のために、各論(各専門)を繋げて総論を組み上げていくのが役割(だとかっこいいな)と思っている。
また、試験合格時には他の技術士(経営工学)の人と会う機会が多かったが、専門が生産管理・品質管理・生産技術だったりと多岐に渡るため、間口の広い分野とも言えるだろう。
身近な経営工学で生産性向上へ
一般的には聞きなれない経営工学だが、経営をよりよくするための技術体系なので、製造業だけではなく、いろいろな人の生活や仕事、勉強の効率化に役立つはずと思っている。
少しでも身の回りの生産性向上に繋がる知識・手法・考え方であれば、身近な経営工学として紹介していくので、何かしらのお役に立つことができれば幸いだ。